伝統的なメディア企業「朝日新聞社」による、Webマーケティング領域のスタートアップ「サムライト」の子会社化。
2016年4月、そのニュースはこれまで日本において見られなかったであろうM&Aのレアケースとして注目を集めました。
しかし、歴史も体制も文化も何もかも異なる両社。3年以上が経過した今、朝日新聞社とサムライトはどうなっているのでしょうか?
そのことを探るべく、“主な情報源は新聞”という環境で過ごしてきた朝日新聞社のアラフォー記者と、“デジタルネイティブ世代”のサムライトの若手社員が、お互いの印象や今後さらにシナジーを生んでいく方法について話し合う場を設けてみました。

松崎敏朗(まつざき・としろう)・39歳(左)
横浜市出身。サムライトではオウンドメディアの企画、取材などを担当。
地方紙を経て2012年、朝日新聞社に入社。秋田→東京→沖縄→広島と赴任し、今年7月から社内プロジェクトの一環としてサムライトに派遣中。
直近の広島では県警のほか広島カープのセ・リーグ優勝に湧く町の様子を取材。2017年にはICAN(核兵器廃絶国際キャンペーン)のノーベル平和賞受賞に際し、授賞式のあるノルウェーへ。
いつまで経っても電子書籍にいま一つ慣れないアナログ人間(自称)。
広部憲太郎(ひろべ・けんたろう)・41歳(中)
函館市出身。サムライトではオウンドメディアのコンサルティング案件、企画、取材などを担当。2000年、朝日新聞社に入社。スポーツ部で朝青龍、亀田興毅ら格闘技系の著名アスリートを追いかけた。
社会部では東京五輪招致や災害などを取材。朝日新聞デジタルの編集者を務めた経験もある。
記者としてのライフワークは、スポーツと地域振興。
今年5月初めまでは、三重県の津総局に所属。おいしいものを食べ過ぎて体重が激増したので、ダイエット中。
大畑滋生(おおはた・しげお)・年齢非公開(右)
静岡市出身。サムライトでは、『SOME JOURNAL』の執筆などを担当。
2005年、朝日新聞社に入社。経済部で電力、鉄鋼、自動車などの「重厚長大産業」ほか、農水省でTPP交渉や小泉進次郎氏の農協改革などを取材。
現在は、朝日新聞メディアラボの新規事業担当としても活動している。社内に「鉄道に詳しい」という噂があるらしく、テツ関連の仕事ばかりまわってくるとのこと。
老舗メディアのアラフォー記者×Webベンチャーの若手。お互いの印象を語る
 樽見
樽見 広部
広部 大畑
大畑 松崎
松崎サムライトは朝日新聞社の子会社ですが、私は特段意識してはいませんでした。未知数な部分がとても多かったので、みなさんと一緒に働くことでサムライトへの理解を深められてきたところです。
逆に岡山さんや樽見さんはどうですか? 派遣が開始されてから、私たちにどんな印象を持っていますか?

岡山里菜(おかやま・りな)・25歳(左)
コンテンツマーケティング事業本部ソーシャルメディア局所属。
教育系企業のSNS運用や美容・健康系メディアの編集者を務める。並行して、企業の採用マーケティングを支援する「SOMERISE for HR」で編集業務に携わる。
4月に開催された半期に1回のサムライト総会では、「ベストグロース賞」を受賞。
樽見一孝(たるみ・かずたか)・24歳(右)
コンテンツマーケティング事業本部オウンドメディア局所属。入社2年目の若きセールス担当。
新卒時は、半年間受注ゼロで苦しみ「給料をもらう資格がありません」と上司に言ったことも。しかし不撓不屈の努力を重ね、オウンドメディア案件の受注金額でサムライト史上最高記録を樹立。いま、乗りに乗っている男。
 樽見
樽見 岡山
岡山 広部
広部嬉しい限りですが、サムライトの業務は幅広いジャンルの仕事を同時並行で処理するので、新聞社と違った大変さがありますよね。
私は住宅系オウンドメディアの企画提案や自社の新規事業である「SOMERISE for HR」に携わっていますが、サムライトで働くうえではWebやオウンドメディアの知識だけでなく、社会に対する幅広い知識を随時キャッチアップしなければいけないと実感しています。
若手社員が先頭に立って、タイムリーな情報を随時拾い上げてビジネスに生かしていく姿勢は、見習うべきだと感じました。
アラフォー記者から見たWebの世界×若手社員から見た新聞。それぞれの強みとは
 広部
広部 岡山
岡山世間では新聞離れが叫ばれていますが、新聞の社会的な信頼性の高さや、記者の方々が持つ専門性や独自の切り口は、デジタルの領域でも存分に価値を発揮するのではないでしょうか?
近年、Googleをはじめとする検索エンジンも、技術面のSEOを徹底しているかどうかよりも、信頼性や専門性が高いコンテンツを評価する流れになっています。そうした流れにうまく乗ることができれば、新聞にあまり興味がないユーザーに対するタッチポイントを増やせそうですよね。
 樽見
樽見ビジネスという観点では、定期購読者数の減少が影響して収益面はかなり厳しいと考えています。また、デジタル化の流れも進んでいますが、紙面の内容をWebに落としただけのケースが多く、Webの強みを生かしきれていない印象です。
なので、ビジネスモデルの転換期ではないかと考えており、朝日新聞社の知見とサムライトのノウハウを合わせ、「新しい新聞のあり方」を確立していけるといいなと思っています。
 松崎
松崎なるほど。若い人たちの客観的で率直な意見はとても参考になります。私たちの世代は、新聞を読むのが常識でした。速報性かつ信頼性が求められる歴史的な事故や政治的な動きの情報を得るには、新聞が一番良いツールだったんです。
物心ついたときからデジタルデバイスで情報を収集する人が増えていくと、正直、これから新聞がどうなっていくのか不安が募っています。
 岡山
岡山 広部
広部広告と記事の境目がなくなっているように感じています。
またSNSなどから各コンテンツに直接アクセスすることが多いことを考えると、内容自体に惹きつけるものがないと読まれないので、そのあたりが難しいですよね。
そういった状況のなか、サムライトは「コンテンツを信じる。」「メディアを進める。」「人を彩る。」というビジョンのもと、Webメディア運営のマーケティング力に長けているなという印象です。
 大畑
大畑 松崎
松崎新聞は自分が書いた記事がどれくらい読まれているのかを把握できませんが、Webの記事はGoogle Analyticsなどで数字を可視化できます。サムライトへの派遣を通して、自分の記事がどうすれば読まれるか? の意識が高まりました。
日本全国のネットワーク×発信力。シナジーが生む、新たな可能性
 広部
広部Webと新聞で土俵は違いますが、それぞれの強みを組み合わせれば、新たなビジネスの可能性を切り開けそうですね。朝日新聞社とサムライトのシナジーって何だと思いますか?
私は、朝日新聞社の強みである地方取材網や営業部隊と、サムライトの発信力を融合し、地方ビジネスを支えられないだろうかと感じています。
5月初めまで、3年間、三重県に拠点を置いて記者をしていました。各地を巡って農林水産業や酒蔵などの伝統産業を取材していくなかで、やる気や商品力があっても、情報の届け方がわからないというケースも目にしました。
たとえば、優れた地方企業の魅力を伝える記事型広告でブランドジャーナリズムができれば、社会への発信力も強まると感じます。
 樽見
樽見実は、先日の会議で朝日新聞社のアセットを活用して、協同で事業を創造したい!という話が出ていました。
サムライトは朝日新聞社の紹介を通じて玄海酒造株式会社の『壱岐日和(いきびより)』というオウンドメディアの運営を支援しています。
朝日新聞社とサムライトがお互いの強みを生かせば、地方を活性化させるメディアや事業を作れそうですね。

▲麦焼酎発祥の地である長崎県・壱岐島。“「島」と「お酒」と「人」のちょっといい話”をコンセプトに、伝統ある壱岐焼酎の美味しさと壱岐という島の心地よさを、ストーリー仕立てのコンテンツを通して発信。(URL:http://www.mugishochu-iki.com/ikibiyori/)
 岡山
岡山明治生まれの朝日新聞社×平成生まれのサムライト。前人未到の挑戦
2019年、朝日新聞社は創刊140周年を迎えました。一方サムライトは、ようやく創業6年を迎えたところ。
明治に生まれた会社と、平成に生まれた会社。生まれた時代背景が異なれば、社風、文化、得意分野などが大きく異なるのは、必然といえるかもしれません。
しかし、だからこそお互いの強みを生かし、シナジーを最大化することができれば、新たな価値を創造し、世の中に提供できるはず。
伝統的なメディア企業である朝日新聞社と「コンテンツを信じる。メディアを進める。人を彩る。」サムライトの前人未到の挑戦は、これからも続きます。いえむしろ、ここからが本番なのです。
「ぜひ一緒にチャレンジしたい!」という熱い思いを持った皆さまからのご応募、お待ちしております。
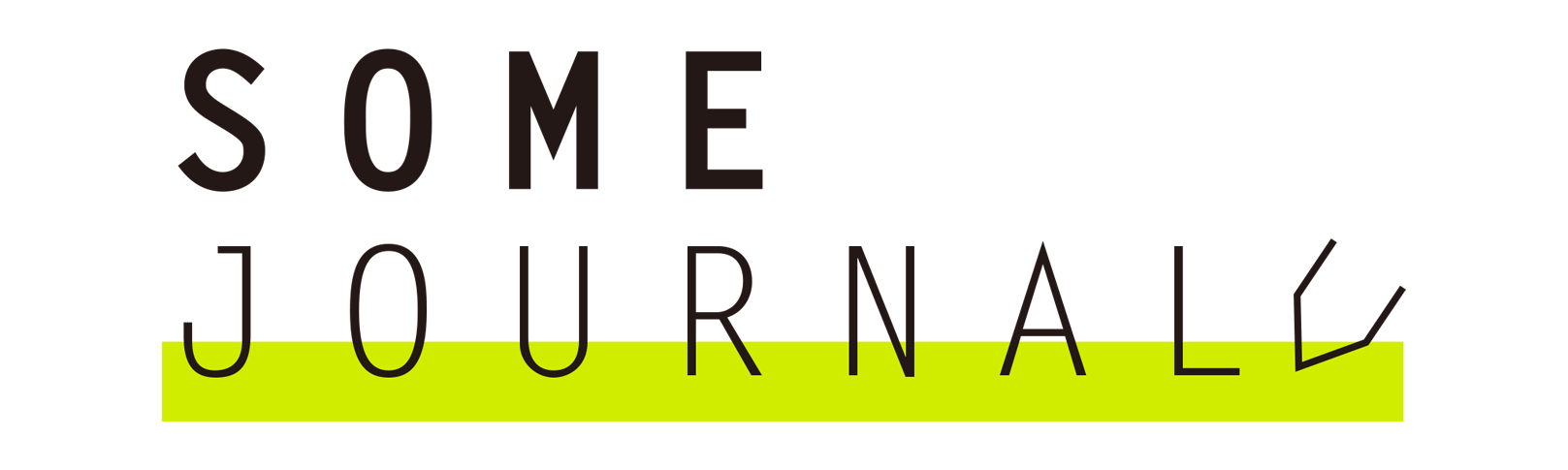






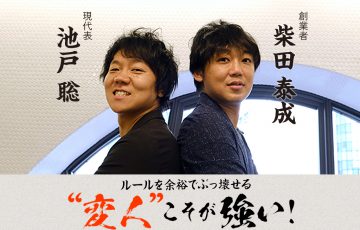



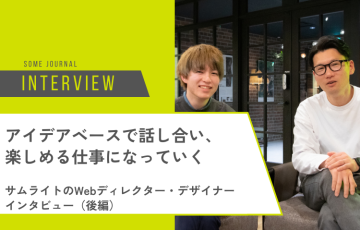
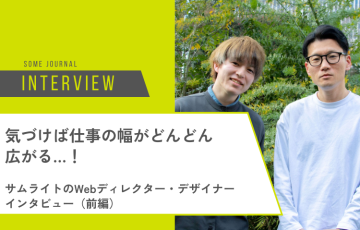
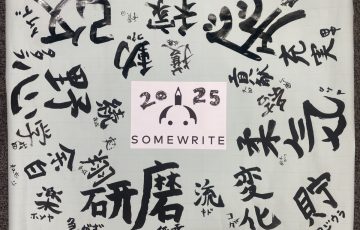

朝日新聞社の方たちが、サムライトに来てから2カ月が経ちましたね。どういう印象をお持ちですか?